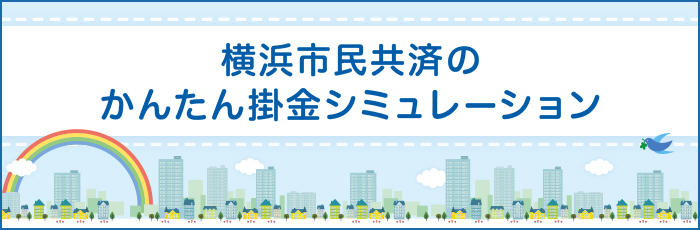災害時の高齢者の避難対策は?事前の備えや避難・避難後の注意点を確認
2022年08月17日

皆さんこんにちは、横浜市民共済生活協同組合です。
災害が発生した際は必要に応じて避難しますが、スムーズに避難するためには日頃からの対策が重要です。
特に、高齢者の場合は避難するタイミングや持ち物、避難所での過ごし方など気をつけなければならないポイントがいくつかあります。
今回は、災害の避難に向けて高齢者がしておくべき備えや、避難時・避難後の注意点についてご紹介します。
目次
- 1.高齢者が災害時の避難に向けて備えておくもの・しておくこととは
- 2.高齢者が災害時に安全に避難するための注意点とは
- 3.災害で避難後に高齢者が注意する点もある?
- 4.まとめ~災害時に高齢者が安全に避難するために、日頃からしっかりと備えを~
高齢者が災害時の避難に向けて備えておくもの・しておくこととは
どの年齢の方でも日頃から災害に向けた対策は必要ですが、高齢者ならではの備えておきたいものや確認すべきポイントがあります。
どのような備えや確認が必要なのか、詳しくご紹介していきましょう。
災害時の避難に向けて「備えておくもの」
災害が起きた際は安全に避難できるように、以下の準備をしておきましょう。
非常用持ち出し袋を準備する
食料や飲料水、貴重品、生活用品など一般的に災害時に持ち出す物に加え、高齢者は以下の持ち物が必要な場合があります。
お粥や介護用のレトルト食品・とろみ剤
嚥下(えんげ)機能が低下している方は誤嚥性肺炎を防ぐために、お粥や柔らかく食べやすい介護用のレトルト食品、とろみ剤などを用意しておきましょう。
おむつ、尿取りパッド
おむつや尿取りパッドは吸収力が高いので、簡易トイレの中に敷くと簡単に処理できます。
断水でトイレが使えない場合もありますので、日常的に使っている方はもちろん、普段あまりおむつを使わない方でも多めに準備しておくと安心です。
普段飲んでいる薬・お薬手帳
血圧の薬や血糖の薬など、疾患によっては飲み続けなければならない薬があります。
どんな薬を飲んでいるのか、本人だけでなく家族も把握しておくことが大切です。
災害時に備えてかかりつけ医や薬剤師と相談し、避難時に必要な薬の種類や数・量を確保しておきましょう。
また、お薬手帳には服薬履歴や健康状態など大切な情報が記載されています。
避難先の薬局でも処方してもらえるように、お薬手帳は日頃からすぐ持ち出せる場所に置いておきましょう。
避難時の持ち物については「避難時の持ち物、最低限準備したいものはこれ!日頃から災害時の備えを」もご参考ください。
災害時の避難に向けて「しておくべきこと」
高齢者の方が災害時にスムーズに、より安全に避難するためには、以下の点を確認・準備しておきましょう。
自宅内の安全対策を取る
素早く安全に避難できるように、自宅内は以下のような安全対策を取りましょう。
- ・背が高くて倒れそうな家具、テレビ・額縁などの重いものや割れものは固定する
- ・窓や戸棚のガラスには飛び散り防止のフィルムを貼る
- ・寝室や逃げ道となる場所に倒れやすいもの・割れやすいものは置かない
- ・開き扉や引き出しには滑り止めシートや扉ロックを使い、中のものが飛び出さないようにする
- ・安全に移動できるように、スロープや手すりを設置する
緊急時連絡カードを作成する
災害などの緊急時に備えるために「緊急時連絡カード」を作成しておきましょう。
住所・氏名・生年月日などの基本情報以外にも、緊急時に連絡してほしい人の連絡先、かかりつけ病院の連絡先、持病や服用している薬などを記入しておきます。
常に持ち歩いておけば、災害以外での緊急時にも役立ちます。
避難行動要支援者名簿に登録する
「避難行動要支援者名簿」とは、災害対策基本法により各自治体に作成が義務付けられている名簿のこと。
高齢者や障害のある方など、自力での避難が難しく支援を必要とする方は事前に申請して登録することで、災害時に地域全体で名簿に登録された要支援者の安否確認や避難支援を行います。
自治体によって登録できる方の基準が異なりますので、登録を希望される方はお住まいの各市区町村にお問い合わせください。
地域の方との交流を持つ
災害時は地域の方との助け合いが重要になります。
日頃から積極的に地域の行事や活動に参加し、近所の方と交流を持ちましょう。
特に地域の防災訓練は参加しておくと、いざというときに行動しやすくなります。
避難場所・避難ルートの危険箇所を確認する
各市区町村が作成している「ハザードマップ」には災害の被害予測図、「防災マップ」には避難所や公共施設などが記載されています。
これらを活用し、避難場所はどこにあるか、災害発生時に安全な避難経路はどのルートなのか、危険な箇所はないかを確認しましょう。
可能であれば事前に下見をしておくと、いざというときより早く安全に避難しやすくなります。
電源が必要な医療機器の非常時の使用方法を確認する
電源が必要な医療機器を使用している方は、停電時に備えて非常時の使用方法を確認しておくことが大切です。
例えば人工呼吸器の場合、停電に備えた外部バッテリーや蘇生バッグがあります。
緊急時にスムーズな対応ができるように、以下のポイントを日頃から確認しておきましょう。
- ・外部バッテリーの寿命や蘇生バッグが劣化していないかを確認し、不備があれば新しいものと交換する
- ・外部バッテリーは常に充電しておく
- ・外部バッテリーの接続方法や蘇生バッグの使い方を確認する
- ・電源異常時にアラームが正しく作動するか確認する
- ・定期的にメーカーのメンテナンスを受ける
その他の医療機器も同様に、非常時の使い方を確認してくださいね。
災害時に安心して避難するためには、日頃からの備えが大切です。
ぜひ上記の内容を参考にしてくださいね。
高齢者が災害時に安全に避難するための注意点とは
災害時の避難のタイミングや場所を誤ると、逆に危険な状態に陥る可能性があります。
高齢者が安全に避難するために、注意点を2つご紹介します。
①避難するタイミングは「警戒レベル3」
災害時の避難情報は各市区町村から発令されます。
テレビやラジオ、ウェブサイト、防災行政無線、緊急速報メールなど、自治体によってお知らせする方法はさまざまです。
2021年5月20日より避難情報は5段階の警戒レベルで伝えられるようになりました。
それぞれの警戒レベルは以下の通りです。
- ・警戒レベル1:早期注意情報(気象庁) 災害への心構えを高める必要がある
- ・警戒レベル2:大雨・洪水・高潮注意報(気象庁) 避難行動の確認の必要がある
- ・警戒レベル3:高齢者等避難 高齢者等は避難する必要がある
- ・警戒レベル4:避難指示 危険な場所から避難する必要がある
- ・警戒レベル5:緊急安全確保 ただちに身の安全を確保する必要がある
警戒レベル1~5のうち、高齢者や障害のある方など避難に時間がかかる方は「警戒レベル3」で避難するようにしてください。
②避難する場所
災害時に避難する場所には、小中学校や公民館など、市区町村が災害の種類ごとに指定した「指定緊急避難場所」があります。
その他にも親戚・知人宅や、ホテル・旅館などの宿泊施設に避難するのも1つの方法です。
これらの場所に避難する際は、安全な場所かどうかハザードマップで事前に確認しましょう。
「今いる場所から移動するのはかえって危険」という場合は、屋内のより安全な場所へ避難する「屋内安全確保」という方法があります。
例えば、津波や浸水のおそれがある場合は自宅の2階やビルの最上階、土砂崩れのおそれがある場合は山からできるだけ離れた部屋といったように、できるだけ安全な場所へ移動しましょう。
災害時は必要に応じて、高齢者や障害のある方など特別な配慮を必要とする方のために「福祉避難所」が開設されます。
福祉避難所は運営体制や受け入れが整い次第開設される避難所なので、災害直後に避難する場合は前述の場所へ各自避難してください。
適切なタイミングや場所を知って、安全に避難してください。
災害で避難後に高齢者が注意する点もある?

災害発生後に避難した場所は、普段と違い慣れないことが多いと思います。
ここでは、高齢者が避難後に気をつけるべきポイントをご紹介します。
身体面の体調管理
避難所や宿泊施設など普段と違う場所での生活は、食欲不振、睡眠不足、血圧の変化、持病の悪化などさまざまな影響を及ぼします。
また、衛生状態が悪化して起こる「感染症」、体を動かさないことで血栓ができる「エコノミークラス症候群(血栓症)」、活動量が減り体を動かしにくくなる「生活不活発病(廃用症候群)」などを発症する可能性もあります。
これらを予防するためには、避難所で以下のことを意識して行いましょう。
- ・規則正しいリズムで食事、睡眠、排泄、薬の服用を心がける
- ・できるだけ普段と同じ量の食事を摂る
- ・手洗い、うがい、消毒をこまめに行う
- ・定期的に体を動かし、水分を摂る
- ・トイレや水分補給を我慢しない
- ・歯磨きやうがい、ガムをよく噛んで唾液を出すなど、口腔ケアを行う
- ・尿道口・肛門付近は濡れたティッシュなどで毎日拭き、下着はこまめに取り替える
- ・介護が必要な方、認知症の方、治療中の方、体調が優れない方などは、何か不安があれば医療・保健スタッフに早めに相談する
精神面の体調管理
普段と違う場所での生活がストレスとなり、心身に起こるさまざまな症状を「リロケーションダメージ」といいます。
年齢に関わらず起こり得る症状ですが、高齢になると環境の変化に対応しにくく、より大きな負担になる方が多いです。
避難所での生活が続くと、以下の症状がみられることがあります。
- ・不眠
- ・うつ症状
- ・不安や混乱
これらの症状を予防するためには、孤立しないようにすることが大切です。
たとえば、避難所の他の方との交流を保つことで、安心感につながります。
また、認知症を患っている方が避難生活を続けると、以下の症状がみられることがあります。
- ・認知症の症状が悪化する
- ・せん妄状態(幻覚や記憶障害など)になる
- ・徘徊する
- ・家に帰りたがる
- ・イライラして落ち着かない
認知症の方には症状が悪化しないように、以下のような対応を心がけましょう。
- ・トイレが近い場所や静かな場所など、本人が少しでも落ち着ける場所を作る
- ・家族や友人など、顔見知りの近くで過ごせるようにする
- ・話しかけるときは正面から顔を近づけ、少し見上げるくらいの角度で接する
- ・接するときは笑顔で対応し、ゆっくりと穏やかな口調で話す
- ・なるべく肯定的な言葉を使い、短い文章で分かりやすく話す
- ・スキンシップをとる際は下から優しく触れる
避難所生活で体調を崩さないためには、できるだけ普段通りのリズムで生活するように心がけてくださいね。
災害時に高齢者が安全に避難するために、日頃からしっかりと備えを
どの年齢の方でも当てはまりますが、災害発生時に安全に避難するためには日頃からの備えが大切です。
特に高齢者は介護用の食品やおむつ、常用している薬や医療機器の予備バッテリーなど、特別な準備が必要になることも。
スムーズに避難するためには、必要に応じて「避難行動要支援者名簿」に事前登録しておく、地域の方との交流を持っておく、緊急時連絡カードを作成しておく、避難場所や避難ルートの危険箇所の確認をしておくなど、安全対策をしておきましょう。
高齢者の避難は「警戒レベル3」で行うことも忘れずに。
また、自宅以外での慣れない環境下で避難生活が続くと、体調を崩しやすくなります。
避難所でもできるだけ普段の生活リズムで、食事・水分・睡眠・排泄・運動を意識して行いましょう。
神奈川県にお住まい・お勤めの方のための「横浜市民共済の火災共済」では、万が一の損害に対する保障や見舞金制度をご用意しています。
ぜひお気軽にご相談ください。