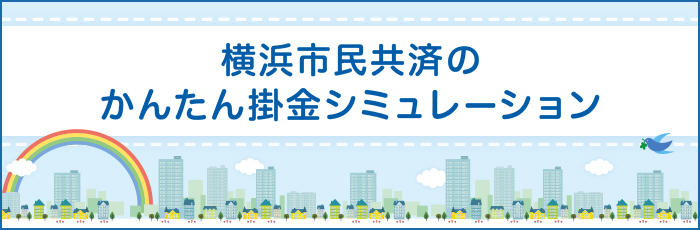避難時の持ち物、最低限準備したいものはこれ!日頃から災害時の備えを
2020年10月30日
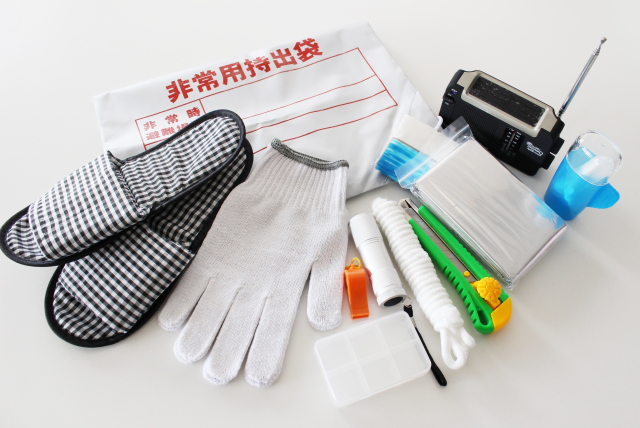
皆さんこんにちは。横浜市民共済生活協同組合です。
日本は地震や台風など災害が多い国です。
万が一の避難に備えて、非常持ち出し袋は準備していますか?
事前にしっかり考えて準備しておかないと「必要なものが入っていなかった!」と後悔してしまう可能性もあります。
今回は避難時の持ち物についてのお話です。
避難時に最低限持っていきたい持ち物、 人によってはあると良い持ち物などをご紹介します。
非常持ち出し袋の中身を一緒にチェックしましょう!
避難時の持ち物は最低限これが必要!非常持ち出し袋を今すぐチェック
まずは、最低限必要!という避難時に必ず持っていきたい持ち物をご紹介します。
飲料水・非常食、水を入れる用の給水袋
飲料水はペットボトルや水缶を準備しましょう。
非常食はアルファ米、缶詰(缶切りを使わなくても開くもの)、カップ麺、栄養補助食品、ビスケットや板チョコなど、常温保存ができてそのまま食べられるものを中心に用意しておきましょう。
水は飲用以外にも洗い物やトイレなどの生活用水が必要です。
給水車から水をもらえるように給水袋も入れておきましょう。
貴重品
印鑑、免許証や保険証、保険証券、通帳のコピー、家族の連絡先など。
免許証や保険証、通帳などは番号がわかるコピーやメモを入れておきましょう。
また、移動や買い物などでカード類が使えず「現金」が必要となることも考えられます。
避難用品
懐中電灯、軍手、ヘルメットや防災頭巾、携帯ラジオ、予備の電池、携帯電話の充電器など。
懐中電灯、軍手、ヘルメットは人数分用意しましょう。
携帯ラジオは手動でも稼働するものにするか、予備の電池を忘れずに。
救急用品
ばんそうこう、マスク、消毒液、包帯、常備薬、持病の薬など。
生活用品
タオル、ティッシュ、ビニール袋、ウェットティッシュ、使い捨てカイロ、紙皿や割り箸、食品用ラップ、ライター、はさみ、ナイフ、携帯用トイレ、トイレットペーパー、新聞紙、筆記用具、など
非常食を食べるための紙皿は食品用ラップを巻いて使い、ラップを取り替えることで衛生的に使えます。
洋服、洗面用具など
衣類、下着、靴下、スリッパ、レインコート、歯ブラシ、毛布など。
両手を使えるようにしておくためにも、避難時の持ち物はリュック一つ背負ってすぐに避難できる量にとどめることが重要です。
飲料水や非常食、生活用品や衣類などは本当に必要なものを選択し、最小限にしましょう。
人によってはこんな持ち物も避難時に必要!
避難時に必要な持ち物は人によっても違います。
こんな持ち物も忘れずに用意しておきましょう。
特に女性、赤ちゃん、高齢者ならではの持ち物は多様にあります。
■女性
・生理用品
・化粧品
■赤ちゃん
・哺乳瓶
・スティックタイプの粉ミルクや液体ミルク
・哺乳びん消毒キット
・紙おむつ
・お尻ふき
・母子手帳
■高齢者
・持病の薬
・お薬手帳
・インスタントのお粥など食べやすい食品
スムーズな避難のために、持ち物以外でも確認しておきたいこと

万が一の災害時にスムーズに避難できるよう、持ち物以外でも普段から災害を想定した準備が必要です。
事前に家族で確認しておきたいことをご紹介します。
避難経路、避難場所の確認
自治体が提供するハザードマップなどを確認し、いざというときの避難経路、避難先を知っておきましょう。
※国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」も参考にしてくださいね。
災害の種類や場所によって通れない場所なども出てくるので、2~3種類の経路を想定し、事前に歩いてみて危険な場所はないかなどチェックしておくと安心です。
狭い道や古い建物、ブロック塀、ガラス張りのビル、川などは危険なので近づかないようにしましょう。
安否確認の方法を確認
家族がバラバラに被災した場合の安否確認の方法を決めておきましょう。
安否確認の方法はうまく利用できない可能性も考え、一つではなく複数用意しておくと良いです。
例えばこんな方法があります。
・自宅の壁やドアに避難先を書いたメモを貼っておく
・災害伝言ダイヤル、災害用伝言板などに記録を残す
・SNSへ情報をアップロードする
自宅を出る際に確認したいこと
自宅から避難所へ行く際には、その後火災が起こる可能性のないよう下記をチェックしてから家を出るようにしましょう。
・ガスの元栓を閉める
・必要のない家電製品のコンセントを抜く
・避難が長期間になる場合や停電時はブレーカーを落とす
避難時の服装や靴
避難時の服装は可能な限り動きやすい恰好で。
台風などによる避難時には長靴は厳禁です。水が靴の中に溜まり動けなくなってしまいます。
動きやすく、足全体を覆うことができるスニーカーで避難しましょう。
避難時の持ち物を再確認!万が一に備えておこう
●災害避難に備えて非常持ち出し袋の中身を再確認。
飲料水や非常食、貴重品、避難用品、救急用品、衣類などまずは最低限の持ち物を備えておきましょう。
持ち物を揃えて終わりではなく、食品の消費期限や電池の消耗度合なども定期的に確認しましょう。
●避難時に必要な持ち物は人によって異なります。
女性は生理用品や化粧品、赤ちゃんは哺乳瓶の粉ミルク紙おむつなども必要です。
高齢者がいる場合は持病の薬はおくすり手帳、非常食も柔らかい高齢者向けのものを用意しておくと良いでしょう。
●いざという時にスムーズに避難できるように、日頃からハザードマップを確認し避難経路や避難場所をチェックしておきましょう。
家族間でも安否確認の方法や合流する避難先などの情報を共有しておきましょう。
避難先へ向かう前には火の元を確認し、ガスの元栓を閉めてから家を出るようにしましょう。
もしもに備えて火災保険の見直し、火災共済への加入をご検討されている方へ。
神奈川県にお住まいの皆様へ安心をお届けする横浜市民共済の火災共済もぜひご覧ください。
家計にやさしい掛金で安心な暮らしを支えます!