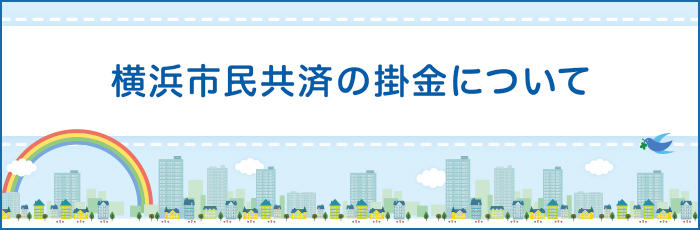強風と暴風の違いは?定義・影響・備えについてもわかりやすく解説!
2022年08月26日

皆さんこんにちは。横浜市民共済生活協同組合です。
台風の時期が近づくと「強風」や「暴風」による影響が気になりますよね。
このよく耳にする「強風」と「暴風」、その違いをご存知でしょうか?
「強風」と「暴風」という言葉は、風の強さによって使い分けられています。
雨や風の強さをきちんと知って被害を防ぐためにも、用語の意味を知ることはとても大切ですよ。
そこで今回は「強風」と「暴風」の違いや主な影響、事前の備えや対策について詳しく解説していきます。
災害が起きた時に備えるためにも、ぜひチェックしてくださいね!
目次
- 1.強風と暴風の違いとは?警報と注意報の違いも解説
- 2.暴風の強さによる影響や被害についてもチェック
- 3.強風や暴風への備えや対処法も知っておこう
- 4.まとめ~強風や暴風の違いを知って災害に備えよう!~
強風と暴風の違いとは?警報と注意報の違いも解説
「強風」と「暴風」、「警報」と「注意報」のそれぞれの違いを解説していきます。
強風と暴風の違い
「強風」と「暴風」は、風の強さによって区別されています。
風の強さの目安は、風速の違いによって0から12までの13階級であらわした「ビューフォート風力階級」が有名です。
この風力階級は世界気象機関(WMO)の風力の標準的な表現法として採択され、日本の気象庁も採用しています。
この「ビューフォート風力階級」によると、「強風」は風速13.9m/s以上17.2m/s未満の
階級7の風で、樹木全体が揺れ、風に向かって歩きにくい状態とされています。
「暴風」は風速28.5m/s以上32.7m/s未満の階級11の風で、めったに起こらない、広い範囲の被害を伴うとされています。
この風速の違いからも「強風」よりも「暴風」のほうが遥かに強い風だということがわかりますね。
暴風警報と強風注意報
注意報と警報の違いは、危険度の違いです。
強風などによって災害が起こる可能性がある場合に「強風注意報」が発表され、それよりもさらに危険性が高く、重大な災害が発生する恐れがある場合に「暴風警報」が発表されるのです。
具体的には、平均風速が約10m/sを超える強風により災害が発生する恐れがあると予想される時に、気象庁より「強風注意報」が発表されます。
しかし、具体的な風速の基準値については都道府県や地域ごとに設定されています。
また、平均風速が約20m/sを超える暴風により重大な災害が発生する恐れがあると予想される時に、気象庁より「暴風警報」が発表されます。
こちらも具体的な風速の基準値については、都道府県や地域ごとに設定されています。
台風と暴風雨の違いは?
「台風」とは熱帯の海上で発生した熱帯低気圧の1つで、北西太平洋または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧区域内の最大風速が約17m/s以上のものをいいます。
一方、「暴風雨」とは台風や低気圧などが原因で起こる暴風に雨を伴う気象現象のことをいいます。
「暴風雨」は台風と違って、明確に風速などの定義があるわけではありません。
「台風」は気象現象の原因となるもの、「暴風雨」はその原因がきっかけで起こる気象現象のことを指します。
風の強さによる影響や被害についてもチェック

気象庁が予報用語として使用している、風の強さと吹き方を表す表現の仕方と、その風でどのような影響や被害が起こるのかを紹介します。
①やや強い風:平均風速10m/s以上15m/s未満
樹木全体や電線が揺れ始め、傘がさせず、風に向かって歩きにくくなります。
高速運転中は横風に流される感覚を受けます。
②強い風:平均風速15m/s以上20m/s未満
電線が鳴り始め、看板などの板が外れ始めます。
雨戸やシャッターが揺れたり、屋根瓦や屋根葺材が剥がれたりすることもあります。
風に向かって歩けなくなり、転倒する人も。
高速運転中は、横風に流される感覚が大きくなります。
③非常に強い風:平均風速20m/s以上30m/s未満
何かにつかまっていないと立っていられず、飛来物によって負傷する恐れがあります。
細い木の幹が折れ始め、看板が落下したり、道路標識が傾いたりする場合もあります。
屋根瓦や屋根葺材が飛散するものがあり、固定されていないプレハブ小屋の移動・転倒や、ビニールハウスのフィルムが広範囲に破れる危険も出てきます。
通常の速度で運転するのが困難になります。
④猛烈な風:平均風速30m/s以上40m/s未満
屋外での行動は極めて危険です。
多くの樹木が倒れ、電柱や街灯も倒れるものが出てくるでしょう。
外装材が広範囲にわたって飛散し、下地材が露出するものがあり、木造住宅が倒壊することもあります。
走行中のトラックが横転する可能性があります。
(参考:気象庁ホームページ)
強風や暴風への備えや対処法も知っておこう
強風や暴風は、台風が原因で発生することから、台風が起こりやすい地域が強風や暴風も多く発生する地域といえます。
日本では7月から10月が台風の発生数が多く、日本の南東の海上で台風の元となる熱帯低気圧が発生しやすくなります。
台風の通り道となりやすい沖縄や九州では、強風や暴風の被害が大きくなることがあり、注意が必要です。
台風上陸が1番多い県は鹿児島県、次いで高知県、続いて和歌山県となっています。
強風や暴風への備え
強風や暴風などの災害はいつ起こるかわからないため、被害を最小限にするためにも事前に備えることがとても大切です。
家の外の備えは風が強くなる前にしよう
確実に強風が来ることがわかっている場合は、以下の備えをしておくと安心です。
- ・庭やベランダに置いてある物干し竿や植木鉢など、飛ばされそうなものは室内に移動しておく
屋外に置いてある自転車もあらかじめ倒して固定しておくか、室内に移動しておく
- ・窓や雨戸、シャッターなどが問題なく使えるか日頃からチェックする。壊れている場合は修理しておく
- ・窓ガラスが割れないようにガムテープやダンボール、飛散フィルムを貼ったり、外側から板で塞ぐ
屋外に置いてある飛ばされそうなものは、全て室内へしまうか固定しましょう。
飛来物などで窓ガラスが割れる可能性があるので、破片が飛び散らないように飛散フィルムを貼ったり、屋根や壁に壊れている箇所がないか確認して修理したりしておくことも大切です。
家の中の備えは日頃からしよう
- ・暴風時外出できないため、食糧や水を備えておく
- ・停電する可能性を想定して、携帯ラジオや懐中電灯、携帯の予備バッテリーなどを備えておく
- ・避難場所と避難経路の確認をしておく
強風や暴風によって木々が倒れて電線がショートするなどして、停電することがあります。
停電や断水に備えて、日頃から準備をしておきましょう。
また、バスなどの交通機関が停止するため、外出しなくても過ごせるくらいの水や食料を準備しておきましょう。
強風や暴風が起きた時の対処法
- ・強風や暴風がひどい時は不要な外出は控える
- ・雨戸やシャッター、カーテンやブラインドを閉める
- ・外出時は交通機関が停止する可能性もあるので早めに帰宅する
- ・車を運転中の場合は、風のあおりや飛来物に注意して、スピードを落とす
- ・河川や海などの危険な場所に近づくことは避ける
- ・河川の近くや土砂崩れが起こりそうな危険な場所にいる場合は、早めに安全な場所に避難する
暴風の中で外出すると、飛来物で大怪我をする可能性があるので大変危険です。
強風や暴風は事前に天気予報をチェックしておくことで備えることができ、被害を最小限にすることができます。
特に台風の多い時期は、災害などの情報をチェックして、日頃から対策をしておきましょう。
強風と暴風の違いを知って災害に備えよう!
「ビューフォート風力階級」によると、「強風」は風速13.9以上17.2m/s未満の階級7の風で、樹木全体が揺れ、風に向かって歩きにくい状態の風とされています。
「暴風」は風速28.5m/s以上32.7m/s未満の階級11の風で、めったに起こらない、広い範囲の被害を伴う風とされています。
このような風速の違いから、「強風」と比べ「暴風」の方が重大な災害などの危険性を伴う強い風を表します。
平均風速が10m/sを超える強風が予想される場合には「強風注意報」、平均風速が20m/sを超える暴風が予想される場合には「暴風警報」が気象庁より発表されます。
飛ばされそうな屋外のものを室内に移動したり、雨や雨戸、シャッターのチェックなどをして備えておきましょう。
また、停電に備えて食料や水を蓄えておいたり、携帯ラジオや懐中電灯、モバイルバッテリーなどを準備しておくと安心ですよ。
強風注意報や暴風警報が発表された際は、飛来物で大怪我をする恐れや転倒する可能性があるので、不要な外出はしないようにしましょうね。
強風や暴風は天気予報をチェックすることで事前に備えることができ、被害を最小限に抑えることができます。
日頃から災害に対しての対策をしておくと、いざという時に困りませんよ。
災害への備えとして、火災保険の見直しも検討してみてはいかがでしょうか。
神奈川県にお住まい・お勤めの方のための火災共済「横浜市民共済」では、台風や暴風等により20万円以上の被害を受けた場合、別途掛金不要の「風水害等見舞金」をお支払いしています。
万が一の被害に備えることも、暮らしの安心のひとつです!
横浜市民共済は横浜市の関係団体として、横浜市危機管理室が公開している「いま」から「いざ」に備える「横浜市避難ナビ」をご紹介しています。
組合員の皆様の安全を守るためのアプリとして、是非ともご活用下さい。
【横浜市避難ナビについて】
横浜市では、ファーストメディア株式会社および学校法人神奈川歯科大学と3者協定を締結し、システム構築やAR技術、マイ・タイムライン作成のノウハウ等を集結したプロジェクトを進め、令和4年3月に「横浜市避難ナビ」を公開しました。
「横浜市避難ナビ」アプリでは、一人ひとりの避難行動計画であるマイ・タイムラインの作成を支援する機能や、「避難所検索」機能、「ARによる浸水状況の疑似体験」機能等があります。災害時には避難情報のプッシュ通知を受信する機能も備えています。